手頃な家賃で賃貸物件を探している方に人気の物件の一つが、軽量鉄骨造のアパートです。
木造のアパートは比較的家賃が安いけれど、防音性や耐久性が気になるという方の中には、軽量鉄骨造であれば安心と考えている方もいるでしょう。
ところが、軽量鉄骨造であっても家族構成やライフスタイル、周辺環境によってはうるさく感じる場合もあり、これを知らずに物件を決めてしまうと後悔する可能性があります。
そこで今回は、軽量鉄骨造のアパートのメリットとデメリット、騒音トラブルを回避するためのポイント、軽量鉄骨造の防音性を高める方法などについてご紹介していきます。
賃貸物件選びをする上で防音性を重視している方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
そもそも軽量鉄骨造とは?

賃貸物件の防音性を左右する最も大きな要素が、建物構造です。
「軽量鉄骨造」の建築構造の1種ですが、賃貸物件を探している方の中には、軽量鉄骨造は防音性が低いと聞いたことがあるため、避けている方もいるのではないでしょうか?
果たして軽量鉄骨造は本当に防音性が低いのか、また建築構造の中で最も防音性が高い構造はどれなのかを解説していきます。
軽量鉄骨造の防音性は木造と同程度
まずは、軽量鉄骨造の特徴と防音性から見ていきましょう。
そもそも軽量鉄骨とは、鋼材の厚さが6mm未満の骨組みを指します。
軽量鉄骨で造られた建物を、「軽量鉄骨造」あるいは「S造」と呼び、そのほとんどが1~2階建てのアパートや住宅です。
軽量鉄骨造と木造の一番の違いは、強度です。
壁や床、天井などに使用する素材はほぼ同じでも、骨組みに軽量鉄骨を用いることで、より高い強度が実現します。
ただし、防音性については木造とそれほど変わりません。
軽量鉄骨造は気密性が高い分、多少は防いでくれるという程度で、上下階および隣室からの足音や生活音、車や電車が通る際の振動音などは、基本的に聞こえるものと考えておいた方が良いでしょう。
その他の建物構造の防音性は?
続いて、軽量鉄骨造以外の特徴や防音性についても見ていきましょう。
木造
骨組みや壁などの主要部分に木材が使用されている建物を木造と呼び、そのほとんどが2階建て以下の住宅やアパートです。
木造アパートのメリットは、他の建物構造よりも建築コストが安いため、家賃を抑えられることです。
また、木材は通気性や吸湿性に優れているので、湿気がこもりにくくカビが発生しにくいのも特徴です。
一方で、気密性が低いため音が外に漏れやすいところがデメリットです。
木造アパートで暮らす場合は、床にカーペットを敷いたり、家具の配置を工夫したり、遮音性能のあるカーテンを利用したりするなどの防音対策が欠かせません。
重量鉄骨造
厚さ6mm未満の鋼材を使用した骨組みを軽量鉄骨と呼ぶのに対して、6mm以上の鋼材を使用した骨組みを「重量鉄骨」と呼び、これを用いた建物構造が「重量鉄骨造」です。
軽量鉄骨よりも厚みのある鋼材を使用するため、強度が必要とされる3階建て以上の建物に多く見られる構造です。
重量鉄骨造は柱が太い分壁も厚くなり、それが緩衝材の役割を果たすため、軽量鉄骨や木造に比べると防音性は高くなります。
ただし、壁自体に防音機能はないため、断熱材やその他の条件によっても防音性は大きく変わります。
RC造
RC造は「鉄筋コンクリート造」の略で、柱や梁、壁、床などが鉄筋とコンクリートで構成されています。
RC造の建物は耐震性と耐火性に優れているのが特徴で、気密性も高いことから建物構造の中では最も防音性に優れています。
気密性が高すぎると結露やカビが発生しやすくなるという心配もありますが、設計の段階でしっかりと計算された建物であれば問題ありません。
RC造の物件は、建築コストが高いことから家賃が高くなりやすいというデメリットがあるものの、防音性を重視する方にはおすすめの構造です。
上記を踏まえて、アパートの代表的な構造を防音性が高い順に並べると以下のようになります。
1:RC構造
2:重量鉄骨造
3:軽量鉄骨造
4:木造
一般的に、隣人の生活音が気にならない壁の厚さは、150~180mmと言われています。
しかし、軽量鉄骨造の壁の厚さは、125mm以下のことがほとんどなので、軽量鉄骨造の物件に住む際は、自分で何らかの防音対策が必要となるでしょう。
軽量鉄骨造のメリット

建物構造の中で最も防音性が高いのはRC構造で、次いで重量鉄骨構造、軽量鉄骨造、最も低いのが木造となっています。
しかし、物件選びの基準は防音性だけではありません。
どの構造にも様々なメリット・デメリットがあるため、それらを総合的に考慮した上で物件を選ぶ必要があります。
ここからは、軽量鉄骨造の物件に住むメリット・デメリットをご紹介していきます。
まず、軽量鉄骨造の主なメリットとしては、次の4つが挙げられます。
・木造よりも防音性が高い
・耐震性や耐久性に優れている
・コストパフォーマンスが良い
・品質が安定している
各メリットについて、詳しく見ていきましょう。
木造よりも防音性が高い
軽量鉄骨造の防音性は、RC造や重量鉄骨造と比べれば劣るものの、木造には勝っています。
木造の場合は、隣室のテレビの音や話し声、上階の足音など何気ない生活音でも聞こえてしまうため、集合住宅では常に音に配慮した生活が必要です。
しかし、軽量鉄骨造であればドアを強く開け閉めしたり、走り回ったりする音は聞こえたとしても、テレビの音や話し声まで漏れることはありません。
小さな子どもがいる場合は心配かもしれませんが、大人が普通に生活する分には特に大きな問題はないでしょう。
ただし、軽量鉄骨造の防音性は個々の建物で大幅に異なります。
例えば、壁や床、天井などに使われている素材や、間取りの他、住民の質によっても違いが出ます。
予算的には軽量鉄骨造の物件を選びたいけれど、騒音が気になるという方は、不動産屋と相談し、できる限り騒音が気にならない物件を紹介してもらうようにしてください。
耐震性や耐久性に優れている
木造と比べれば、防音性だけでなく耐震性や耐久性についても、軽量鉄骨造の方が優れています。
柱が鉄骨であることから、地震の際は木造よりも揺れが大きく感じることがありますが、軽量鉄骨造に使用される鋼材には柔軟性があり、揺れることによって地震のエネルギーを吸収しているため、倒壊するようなことは滅多にありません。
設計などによる細かな違いはありますが、RC造や重量鉄骨造ほどではないにしろ木造よりは耐震性や耐久性に優れているのが軽量鉄骨造の特徴です。
コストパフォーマンスが良い
軽量鉄骨造のメリットは、何といってもコストパフォーマンスが良いことです。
RC造や重量鉄骨造は、防音性に優れてはいますが、建築コストが高いため家賃も高めに設定されていることが多いです。
一方、軽量鉄骨造の場合は、「プレハブ工法」と言って工場で大量生産したものを現地で組み立てる方式で建てられるため、建築コストが安く家賃も手頃な傾向にあります。
そのため、家賃は抑えつつも木造よりは防音性が高く耐震性に優れた物件に住みたいと考えている方には、ピッタリの構造と言えます。
品質が安定している
上記でもご説明したとおり、軽量鉄骨造は「プレハブ工法」によって建てられているため、メーカーや職人の腕に左右されることなく品質が安定している点もメリットです。
あらかじめ工場で生産した材料を、現地で組み立てるだけなので、他の構造よりも短い工期で完成します。
建築材料は風雨や紫外線にさらされる時間が長くなるほど、品質が低下していってしまいますが、それを最小限に抑えられるところも品質の安定につながっています。
軽量鉄骨のデメリット
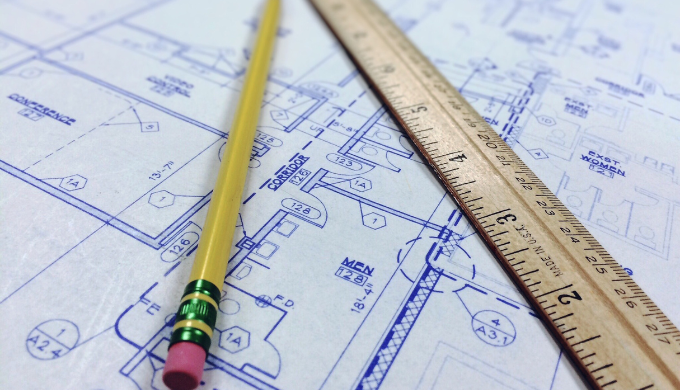
続いて、軽量鉄骨造のデメリットについても把握しておきましょう。
軽量鉄骨造の主なデメリットは、次の4点です。
・防音性に不満を感じることもある
・RC造に比べて断熱性が低い
・木造よりも通気性が悪い
・メンテナンスが不十分だと劣化しやすい
それぞれのデメリットを、以下で詳しく解説していきます。
防音性に不満を感じることもある
軽量鉄骨造の防音性は、木造に比べれば高いものの、RC造や重量鉄骨造よりは劣ります。
RC造の場合は、コンクリートを流し込んで造られており、壁と床とのすき間がなく気密性が高いため、音漏れしにくい構造となっています。
また、重量鉄骨造の場合は、太い柱に合わせて壁も厚くなっているため、たとえ同じ素材を使っていたとしても軽量鉄骨造よりは音が伝わりにくいです。
しかし、軽量鉄骨造の場合は、重量鉄骨造よりも壁が薄い上に、鉄骨造特有の骨組みを造ってから壁や床をつけるといった建て方をしていることから、隙間ができやすくなっています。
そのため、物件によっては軽量鉄骨造でも木造とあまり変わりなく、隣人の生活音がうるさく聞こえることもあります。
特に、以下に当てはまる方は注意が必要です。
・周囲の音に敏感
・来客が多い
・小さな子どもがいる
・ペットを飼っている
上記に当てはまる場合は軽量鉄骨造ではなく、重量鉄骨造かRC造の物件を選ぶことをおすすめします。
RC造に比べて断熱性が低い
軽量鉄骨造は鉄骨造の特性上、断熱材のすき間ができやすいため、RC造に比べて断熱性が低い点もデメリットです。
特に、ベランダや外階段のように鉄骨が露出している部分が多い建物は、外の熱が室内に伝わりやすい傾向にあります。
夏は室温が上がりやすく逆に冬は室温が下がりやすいことから、冷暖房費がかさみがちです。
また、1階は地面から寒さが伝わりやすいので、寒さが苦手という方は2階以上の部屋を選ぶのがおすすめです。
反対に最上階は屋根からの熱が伝わりやすいので、暑いのが苦手という方は、下の階を選ぶなど、階数の違いによる影響も考慮して部屋選びを行いましょう。
断熱シートや断熱カーテンなどを利用した対策も可能ですが、そうした対策に費用や労力をかけたくない方は、最初から断熱性能が高いRC造の物件を選ぶことも賢い選択方法の一つです。
木造よりも通気性が悪い
木造に比べて通気性が悪い点も、軽量鉄骨造のデメリットの一つです。
通気性が悪いと熱や湿気が部屋にこもりやすく、外と室内の温度差が大きくなって結露が多く発生します。
そのため、カビが繁殖しやすく、こまめに掃除をしないと健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。
ただし、壁に調湿材の高い素材を使用している物件であれば、ある程度は結露の発生を防げるでしょう。
また、室内に洗濯物を干すなどで湿度が高くなった時には、その都度換気扇を回すなど部屋の湿度をできるだけ外に逃がす工夫をすることでも、カビの発生を抑えられます。
とはいえ、通気性が悪い住宅はダニも発生しやすいので、アレルギー体質の方でそれほど防音性にこだわらないのであれば、木造物件も選択肢に入れてみてください。
なお、通気性が悪いということはデメリットだけではありません。
室内の温度が逃げにくいので、エアコンの冷暖房の効きが良くなるというメリットも得られます。
メンテナンスが不十分だと劣化しやすい
鉄骨は錆びやすく熱に弱いという特性があるため、メンテナンスが不十分だと建物の劣化が早まってしまいます。
鉄骨造のアパートのメンテナンスで特に重要なのが、定期的な塗料の塗り替えです。
鉄骨塗装のやり方は、まず下地に防水材を塗ってから耐候性のある塗料を塗布するのが一般的です。
鉄骨塗装には見た目を良くする他、錆びや腐食を防止する効果があります。
しかし、時間の経過とともにどうしても劣化していくので定期的に塗り替える必要があるのです。
塗料の劣化を放置すると、やがて雨水が侵入するようになり、建物内部まで傷めることになりかねません。
建物内部の鉄骨が錆びて膨張すると、外壁にひび割れが発生し、建物の耐久性が著しく低下してしまいます。
安全な生活が送れるようにするためには、軽量鉄骨造であってもその他の構造であっても、きちんと定期的なメンテナンスが実施されている物件を選ぶようにしましょう。
ちなみに、鉄骨造のアパートの法定耐用年数は、鋼材の厚みが3mm以下の場合は19年、3mm以上4mm以下であれば27年、4mm以上は34年とされています。
また、その他の構造では木造が22年、RC造が47年となっています。
法定耐用年数とはあくまでも、建物の減価償却が行える期間であり、多くの建物は法定耐用年数を超えても適切なメンテナンスが行われていれば住み続けることが可能です。
トラブルを回避するための事前チェックポイント

軽量鉄骨の物件は家賃が比較的安価なので、住みやすいイメージがあるでしょう。
しかし、軽量鉄骨ならではのメリットやデメリットがあり、防音性の構造を知らないで契約してしまうと後悔することもあるでしょう。
もし、軽量鉄骨の物件に住んだ場合は、トラブルに遭遇する可能性も視野に入れておくべきです。
そして、トラブルを回避するためのポイントを把握しておきましょう。
周辺の環境について知っておく
軽量鉄骨の物件を選ぶ際には、周辺の環境について知っておきましょう。
建物の防音性が高かったとしても、周辺に大きな音を出すものがあれば聞こえてしまいます。
実際に賃貸物件のある現地に行き、道路や電車などの音が聞こえるか、駅の近くではないか、幹線道路からの距離はどれくらいかなどを確認してみてください。
幹線道路沿いの場合は、1日中車や電車の行き交う音があり、遮断機の警報音が聞こえてくる場合もあります。
風向きで音の大きさが変わることもありますが、音以外にも線路が近いと電車の往来による振動が伝わってくることもあるでしょう。
他にも隣家との距離が近い場合、生活音がする可能性も考えられます。
学校や保育園が近い場合は平日の通学時間帯が賑やかですが、平日の昼間のみです。
工場や作業場などが近い場合は、稼働時間によって作業音が夜中まで聞こえてくる場合もあります。
駅や職場から近い物件は、利便性が高いケースも多く魅力的ですが、賃貸物件の位置によっては利便性が生活の質を下げてしまう可能性もあるでしょう。
周辺の環境を知っておくことで、デメリットが見えてくる可能性もあるのでチェックしてみてください。
交通状況を体感しておく
周辺の道路状況や鉄道などの交通状況なども、実際に物件の近くで体感しておくのがおすすめです。
ただし、1回行っただけで安心してはいけません。
昼間と夜間、曜日によって現地で気になる音は変わってきます。
平日の昼間は静かな環境であっても、夜になるとトラックなどの音が響いたり、エンジン音が聞こえてきたりする場合もあります。
また、朝と夕方の通勤や通学ラッシュ時には幹線道路からの抜け道に使われるケースもあり、頻繁に車がスピードを出して通り抜けていく道路もあるでしょう。
このように、特定の時間や曜日によって環境が変化して騒音が現れる光景は珍しいものではありません。
1度チェックしただけではわからないことが多い場合は、複数回時間や曜日を変えて訪れるのが良いでしょう。
騒音トラブルについて確認しておく
賃貸物件の場合、他の部屋の住人についても把握しておくと安心です。
過去に騒音が大きなトラブルとなったことがあるかもしれません。
できるなら、近所に住んでいる方に過去何かあったかを聞けるのが理想ですが、いきなり聞くのはハードルが高いだけでなく、相手も「この賃貸物件で何かあったのか?」と疑わせてしまうかもしれません。
また、何かがあったとしても初対面の相手に教えてくれない可能性も考えられます。
そのため、不動産会社に騒音についてのトラブルがあったかどうかを必ず確認しておきましょう。
不動産会社から近隣の住民に聞いてくれる可能性もあります。
もし、この騒音に関するトラブルが賃貸物件の中で起こった場合は建物の構造に問題がある可能性も考えられます。
不動産会社には重要事項説明責任があるため、事前に問題を把握していた場合は説明してもらえるでしょう。
建物の構造上、騒音を抑えにくい場合は改善するのは難しいです。
音について心配な場合は、壁を叩いて高い音がしないか、窓の取り付け位置や防音性能がついているか確認してみてください。
壁から高い音がした場合は中が空洞になっているため、防音性能には期待できません。
物件の築年数や間取りについても知っておく
築年数が新しい物件には、建築した時に最新の技術が使われています。
そのため、築20年の物件と築5年の物件では、築5年の物件の方がすべてにおいて新しい技術や改善点が反映されているのです。
ハウスメーカーでは、年々新しい技術や独自の手法を取り入れていることも多く、防音性についても配慮しています。
もし物件の施工会社がわかる場合は、ホームページなどから防音性についての技術を調べておくのがおすすめです。
他にも、隣家の間取りも音に対して関係してきます。
隣家同士の間取りで、居室が離れている場合は生活音が響きにくくなります。
鏡に写したように反転した間取りや、隣家との間に収納スペースが挟んである間取りであれば生活音が気になりにくいです。
最上階や角部屋なども音が気になりにくくなっています。
隣家の間取りがわからない場合は、不動産会社に確認してみましょう。
軽量鉄骨はうるさい?防音性を高めるには?

軽量鉄骨は音についてデメリットになる一面がありますが、知らずに入居してしまった場合は自分自身で少しでも快適に生活できるように対策を取りましょう。
防音対策は、自分自身でも取り入れることができるものもあります。
ここでは、防音性を高めるための方法をご紹介します。
防音シートを貼る
防音シートを壁に貼ると、騒音をかなり抑えられます。
これは、自分の部屋で出た音も周囲に抑えられるという意味です。
音以外にも壁の薄さや施工の悪さなどで、騒音が伝わりやすい物件ももちろんあります。
しかし、防音シートなら貼るだけで効果を感じやすく、両方の音をシャットアウトできるので便利です。
現在防音シートは、おしゃれなものも多くなっています。
DIYで使う方も多く、貼ったり剥がしたりできて見た目もおしゃれです。
防音対策以外にも、部屋の印象を変えたり壁の傷防止にも取り入れたりできるため、好みのシートを探してみましょう。
床にマットやカーペットで音を緩和する
床が薄かったり、建物によっては足音で起こる振動音が下に響きやすかったりします。
床に防音カーペットやマットを敷くことで響く音が緩和され、遮音効果が高くなります。
小さな子どもがいる場合、大人のようにスリッパを履いて歩くわけにいかないので、マットやカーペットが1枚あるだけで下に響く音が変わります。
防音カーペットには、遮音等級と呼ばれる防音性能が定められていて、ΔLL値で示されているので他の機能と合わせて選ぶと快適になるでしょう。
防音カーペットだけでなく防音畳もあるので、空間によっては防音畳に変えるのもおすすめです。
背の高い家具を壁面に置く
背の高い本棚などは、壁面に置くことで防音対策ができます。
家具の厚みがあればその分音を遮る壁が厚くなり、生活スペースと離れれば騒音も聞こえにくくなるでしょう。
新しく家具を購入して備え付けることもできますが、元々あった家具でも問題ありません。
クローゼットや本棚、タンスなど、奥行きと高さがある家具ならどれでも問題ないでしょう。
背の高い家具を壁面に置く場合は、地震対策用の棒を天井と家具の間に設置すると、安全性も高まるのでおすすめです。
洗濯機や冷蔵庫に防振マット
夜間に洗濯機を回すことはありますが、時間帯によってはトラブルになる可能性も考えられます。
洗濯機が回る音以外でも、キッチンでは冷蔵庫のモーター音が気になるという方も少なくありません。
このような振動音やモーター音対策には、防振マットを使うのがおすすめです。
本来、夜遅い時間に洗濯機を回すのは良くありませんが、帰宅後でないと洗濯できない方もいます。
洗濯機を夜使うのがメインの場合は、足の下に防振マットを使うと便利です。
マットの大きさにもよりますが、ネット通販などでも簡単に手に入ります。
音の出る機器は壁から離す
テレビやオーディオなどは、壁から遠く離した位置に置きましょう。
特にテレビの場合、スピーカーなど音が出る部分が背面側にあるため、壁を通じて隣にまで音がする可能性があります。
できるだけ音が出る部分は、隣の部屋に通じる壁から離すようにしましょう。
1DKなど設置する位置が限られてしまう場合は、部分的に遮音シートを貼る、吸音マットを敷くなどして、周囲への配慮を意識してみてください。
家事の時間帯に気を付ける
洗濯機以外にも掃除機や扉の開閉音、給排水の音などは気を付けましょう。
朝早く料理をした場合、キッチンからの音や衝撃音、動く音などがしやすいです。
特にまだ周囲が起きていない時間帯は、音も響きやすいのでいつもなら気にならない部屋まで届く可能性があります。
料理は仕方ないかもしれませんが、できるだけ家事をするのは早朝や深夜の時間帯は控えましょう。
また、動きのある位置にはマットを敷くなどの配慮が大切です。
スリッパを使用する
何気なく歩いている音でも、想像以上に音が下の階に響いている可能性があります。
特に子どもがいる場合は、走ったり飛び跳ねたりする音と振動を大きく感じるかもしれません。
このような固体音は苦情になる可能性が高いので、できるだけ部屋の中ではスリッパを使って衝撃が起こりにくいように工夫しましょう。
子どもなら厚手の靴下でも効果的です。
隙間テープを使う
扉や窓の隙間は、音の振動が伝わりやすい部分です。
閉めた状態でも窓や扉がガタガタ動く場合は、隙間テープを使うと音の侵入を防ぐだけでなく、振動を吸収します。
ドアの開閉などで出てしまう生活音が簡単に軽減できるでしょう。
防音カーテンを取りつける
窓から音が入ってきたり漏れてしまったりすることも多いのですが、見落としがちな部分でもあります。
そんな窓には防音対策カーテンを取り付けてみましょう。
防音対策カーテンは、音を吸収や吸音するだけでなく、遮音効果も持っています。
中高音域の音を防ぎやすく、プライバシーに配慮できたり、赤ちゃんの泣き声が気になったりする方におすすめです。
踏切の音やピアノの音などにも効果を発揮するので、音が気になる方は防音カーテンで遮光性と同時に音も遮断してみましょう。
苦情を受けた時の対処法も把握しておこう

苦情を受けた場合、相手に対してきちんと謝罪しなければなりません。
最初の姿勢はとても大切なものとなりますが、このように苦情を受けた場合はどのように対処すべきでしょうか?
詳しい情報を聞く
騒音トラブルが起こった場合は、できるだけ細かな情報を聞きましょう。
いつ頃、何時頃の出来事かを聞き、寄せられた内容について心当たりがある場合はすぐに改善してください。
「朝早い時間に掃除機をかけないで欲しい」「洗濯機を夜中に回すのをやめてほしい」など、生活サイクルに関するものであれば時間を見直す必要があります。
改善されないと再度苦情を言われたり、さらに問題が悪化してしまったりする可能性も考えられます。
直接苦情を言いに来ることは少なく、その多くは管理会社や不動産会社を通じて伝えられることが多いです。
直接言われた場合は、大きなトラブルに発展する可能性もあるので慎重に対応しましょう。
不動産会社に相談する
騒音に心当たりがない、その時間帯はすでにいないなど、思い当たることがない場合は管理会社もしくは不動産会社に相談してみましょう。
実は、上から聞こえてくる騒音であっても真上ではない可能性もあります。
特に音や振動の発生源は特定が難しく、まれに勘違いされている場合もあるので、騒音の情報を聞いて心当たりがない場合はきちんと伝えてください。
そのまま放置してしまうと、自分ではない騒音の発信源にされたままになってしまいます。
当事者同士の言い争いを防ぐためにも、きちんと伝えておくようにしてください。
軽量鉄骨の物件に限らず、賃貸物件では騒音問題やトラブルが起こる可能性が高いです。
「うるさい」「振動音が響いてくる」など、騒音に関する問題が起こった場合は、できるだけ早めに対処する必要があるでしょう。
木造住宅と同レベルの防音性なので、どうしても周囲の生活音が響きやすいです。
自分自身でも生活音が周囲に迷惑にならないように、防音対策を取ってみましょう。
特に壁面と床には防音マットや畳、シートなどを取り入れた対策がおすすめです。
DIYの流行もあり、おしゃれな防音壁面シートもあるので模様替えとしても楽しめます。
賃貸物件でも使用できるシートがほとんどなので、これらの対策を取って楽しみながら防音してみてください。




