住宅をリフォームする場合、施工内容によっては数百万円以上の高額な費用がかかってくる場合もあります。
そのため、リフォーム費用をまとめて用意するのが難しい場合もあるでしょう。
しかし、リフォームローンを活用すれば毎月の支払いは発生するものの、高額なリフォーム費用をまとめて用意する必要がなくなります。
そんなリフォームローンを利用する場合、住宅ローンと同様に控除は受けられるのでしょうか?
今回は、住宅ローン控除をリフォームローンにも活用できるのか解説しつつ、その他リフォームに活用できる控除制度や確定申告の流れ、注意点などをご紹介します。
リフォームローンを利用する際に、控除でうまく税負担も抑えたい方はぜひ参考にしてみてください。
目次
リフォームに住宅ローン控除は活用できる?

そもそもリフォームで住宅ローン控除を活用できるのか、疑問に思っている方も多いでしょう。
結論から言えば、リフォームも住宅ローン控除が適用されます。
ただし、適用されるためには条件を満たす必要があります。
ここでは、住宅ローン控除の解説から、住宅ローン控除をリフォームで適用させるための条件についてご紹介します。
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除とは、住宅ローンによって自宅を購入した場合、一定期間において年末の住宅ローン残高に応じた金額が所得税・住民税の一部から控除される制度です。
最大975,000円までなら控除することができます。
住宅ローン控除の計算方法
実際にどれくらいの控除額になるのか、計算方法を把握しておきましょう。
まず、住宅ローン控除は年間の最大控除額、借入限度額から計算した借入残高の一定割合、所得税・住民税の合計金額のいずれか少ない金額が適用されます。
基本的には収入も変動するもので、住宅ローンの残高も徐々に減っていくことから、控除額も毎年変動していきます。
・年間の最大控除額
リフォームの年間最大控除額は14万円です。
認定住宅をリフォームした場合は21万円までになります。
・借入残高の一定割合
借入残高の一定割合を算出するためには、年末のローン残高に0.7%を掛けることで算出できます。
例えばその年のローン残高が500万円だった場合、500万円×0.7%=35,000円です。
・所得税・住民税の合計金額
所得税と住民税は、所得や扶養などによって異なります。
なお、所得税・住民税から控除される時、まずは所得税から控除され、控除額がまだ残っている場合は住民税の一部(最大97,500円)から控除になります。
納付額を超えて還付されることはないので注意してください。
住宅ローン控除をリフォームで適用させるための条件
住宅ローン控除をリフォームで適用させるためには、以下の条件をクリアしなくてはなりません。
・自身が所有し、なおかつ居住している家
・リフォーム工事が完了してから6ヶ月以内に入居している
・リフォーム工事後の床面積が50㎡以上ある
・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下
また、併用住宅(居住用と業務用の2つの空間が合わさった家)の場合は床面積の2分の1以上が居住用スペースとして活用していなければなりません。
住宅ローン控除が適用されるリフォームの対象工事
リフォームの種類は多岐にわたりますが、すべての工事が住宅ローン控除の対象になるわけではありません。
住宅ローン控除が適用されるリフォームの対象工事は、以下のとおりです。
| 第1号工事 | 増築や改築、建築基準法に則って行う大規模修繕、模様替え |
| 第2号工事 | マンションで区分所有するスペースであり、床や階段、間仕切り、主要構造部の壁などいずれかの過半で行う修繕・模様替え |
| 第3号工事 | 居室やキッチン、浴室、トイレ、その他部屋の床や壁のすべてを修繕または模様替え |
| 第4号工事 | 一定の耐震基準にするための修繕・模様替え |
| 第5号工事 | バリアフリーを目的とした改修工事 |
| 第6号工事 | 省エネ性能を高める改修工事 |
ただし、リフォーム費用から補助金を引いた時の金額が100万円以上になっている必要があります。
さらに、建築士や指定確認検査機関から認定されているリフォーム工事でなければなりません。
これは住宅ローン控除を受けるために証明書が必要となるためです。
住宅ローン控除が適用された場合の借入限度額・控除期間
リフォームに住宅ローン控除を適用させた場合、控除対象となる借入限度額は2,000万円になります。
また、控除期間は10年間です。
控除率は0.7%になるため、実質10年間で受けられる控除額は最大140万円になります。
住宅ローン控除がリフォームに適用されるケース・できないケース

住宅ローン控除についてご紹介してきましたが、いざ自分事として考えた時、本当に当てはまるのかどうかわからない方も多いでしょう。
そこで、住宅ローン控除がリフォームに適用されるケース・できないケースについてご紹介します。
中古住宅を購入してからリフォームする場合
新築物件だと希望するエリアに建てるのが難しい場合、希望するエリアの中から中古住宅を選び、新築に近い形にリフォームできます。
これなら希望するエリアで、ほぼ新築と変わらない住居を手に入れられます。
中古住宅を購入する際にも住宅ローン控除が適用されますが、実は中古住宅を購入した場合の住宅ローン控除と、リフォームによる住宅ローン控除は併用することが可能です。
ただし、併用させるためには両方の条件をすべて満たしている必要があります。
中古住宅を購入する場合で控除を適用させるための条件は以下のとおりです
・建築後使用歴がある
・贈与もしくは生計を共にする人から取得した物件ではない
・リフォームまたはリノベーション工事が完了してから6ヶ月以内に居住している
・住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで住んでいる
・住宅ローン控除を受ける年の所得合計額が2,000万円以下
・住宅の床面積が50㎡以上
・住宅の床面積の2分の1以上が居住用
・借入金の返済期間が10年以上
・併用負荷の減税特例を受けていない
・金融機関などの住宅ローンを活用している
・建築から購入までの期間が20年以内(耐火建築物は25年以内)
ただし、20年以上であっても、購入する2年以内に現行の耐震基準の適合が証明されている1982年以降に建築されている住宅なら控除対象になります。
親名義の自宅をリフォームする場合
例えば実家が親名義になっており、一緒に住んでいるためリフォーム費用は自身が負担した場合、住宅ローン控除は受けられなくなります。
なぜなら、住宅ローン控除が適用される条件として、自身が所有している必要があるためです。
親子関係にあったとしても、名義が自分自身になっていない場合は住宅ローン控除が適用されないので注意してください。
また、このケースでは親名義の自宅を子どもが費用を出しているため、贈与しているとみなされ、贈与税が発生します。
控除が適用されないだけでなく、贈与税まで発生してしまうので、リフォームをするなら最初に名義を変更しておいた方が良いです。
住宅ローンを利用していない場合に活用できる「リフォーム促進税制」

上記はあくまでも住宅ローンを利用している場合に受けられる控除制度になりますが、リフォームでローンを利用していなくても適用される控除制度があります。
ここからは、リフォーム促進税制について詳しく解説していきましょう。
リフォーム促進税制とは?
リフォーム促進税制とは、対象のリフォームを行った際に、所得税の税額控除を受けられる制度です。
住宅ローン控除とは異なり、控除期間は工事が完了した年(1年間)のみになります。
また、リフォーム促進税制の控除額や要件は対象となる工事によって異なるものの、最大105万円までです。
さらに控除額を計算する上で、実際にかかった工事費用ではなく各工事で定められている、標準的な工事費用相当額から計算されるので注意してください。
リフォーム促進税制は住宅ローン控除に比べると、控除額的にはそこまでお得とは言えません。
しかし、住宅ローンを使っていない人でも利用できる制度なので、うまく活用して所得税の負担を抑えましょう。
リフォーム促進税制の種類
リフォーム促進税制は各工事によって条件などが異なります。
ここからはそれぞれの種類と適用を受けるための条件について解説していきましょう。
・耐震リフォーム
耐震リフォームの場合、旧耐震基準(1982年5月31日以前)で建てられた住宅に対して、現在の耐震基準に適合させるリフォームを行った場合、所得税の税額控除が受けられます。
税額控除を受けるための要件は以下のとおりです。
・耐震リフォームを行う人が対象の家に居住している
・リフォーム前の家屋が現在の耐震基準に適合していない
・対象の家が1982年5月31日以前に建てられている
・現在の耐震基準に適合させるためのリフォーム工事である
・2025年12月31日までに施工が完了している
・その他減税を受けたい増改築工事がある場合、その工事は減税対象の工事になっている
・5%に相当する所得税控除を受ける場合、自身が所有する家で、なおかつその年の合計所得金額が2,000万円以下
耐震リフォームの最大控除額は62.5万円です。
・バリアフリーリフォーム
対象のバリアフリー工事を行うことで税額控除が受けられます。
対象工事は以下のとおりです。
・通路の拡幅
・階段の勾配緩和
・浴室・トイレの改良
・手すりの取り付け
・段差の解消
・出入口の戸の改良
・床材の取り替え
また、税額控除を受けるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
・リフォームを行う人が以下いずれかに該当すること
①50歳以上
②要介護・要支援認定を受けている
③障がいを持っている
④②・③または65歳以上のいずれかに該当する親族と同居している
・バリアフリーリフォームを行う人が所有・居住している家である
・リフォーム後の床面積が50㎡以上
・床面積の2分の1以上が居住用
・バリアフリーリフォームにかかる標準的な工事費用相当額から、補助金などを差し引いた金額が50万円を超えている
・2025年12月31日までに改修工事が完了し、居住している
・工事を行った年の合計所得金額が2,000万円以下
・その他減税を受けたい増改築工事がある場合、その工事は減税対象の工事になっている
・バリアフリーリフォームが完了してから6ヶ月以内に居住している
バリアフリーリフォームの最大控除額は60万円です。
・省エネリフォーム
対象の省エネリフォーム工事を受けることで、税額控除が受けられます。
対象工事は以下のとおりです。
・窓の断熱改修(必須)
・天井、壁、床の断熱改修
・太陽熱を利用した冷温熱装置の設置
・高効率給湯器(エコキュートなど)の設置
・高効率エアコンの設置
・太陽光発電設備の設置
また、税額控除を受けるためには、以下の条件を満たさなくてはなりません。
・省エネリフォームを行う人が所有・居住している家である
・リフォーム後の床面積が50㎡以上
・床面積の2分の1以上が居住用
・省エネリフォームにかかる標準的な工事費用相当額から、補助金などを差し引いた金額が50万円を超えている
・2025年12月31日までに改修工事が完了し、居住している
・工事を行った年の合計所得金額が2,000万円以下
・その他減税を受けたい増改築工事がある場合、その工事は減税対象の工事になっている
・省エネリフォームが完了してから6ヶ月以内に居住している
断熱工事または高効率空調機の設置工事などの最大控除額は62.5万円です。
一方、上記の省エネリフォームに加えて太陽光発電設備の設置工事を行った場合、最大控除額は67.5万円まで上がります。
・同居対応リフォーム
同居するためにリフォーム工事を行った場合も、条件を満たしていれば控除を受けられます。
キッチンや浴室、トイレ、玄関の増設工事が対象となります。
同居対応リフォームで控除を適用されるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・同居対応リフォームを行う人が所有・居住している家である
・リフォーム後の床面積が50㎡以上
・床面積の2分の1以上が居住用
・リフォーム後、キッチンや浴室、トイレ、玄関のうち、いずれか2ヶ所以上が複数存在している
・同居対応リフォームにかかる標準的な工事費用相当額から、補助金などを差し引いた金額が50万円を超えている
・2025年12月31日までに改修工事が完了し、居住している
・工事を行った年の合計所得金額が2,000万円以下
・その他減税を受けたい増改築工事がある場合、その工事は減税対象の工事になっている
・同居対応リフォームが完了してから6ヶ月以内に居住している
同居対応リフォームの最大控除額は62.5万円です。
・長期優良住宅化リフォーム
長期優良住宅化リフォームは、住宅の耐久性を向上させるための工事を行い、なおかつ長期優良住宅の認定を取得することで控除が受けられます。
また、省エネリフォームでご紹介した対象工事も行っている必要があります。
耐久性を向上させるための対象工事は以下のとおりです。
・小屋裏の換気性の向上(木造・鉄骨)
・小屋裏の点検口の取付(木造・鉄鋼津)
・外壁を通気構造などにする工事(木造)
・浴室または脱衣室の防水性向上(木造)
・土台の防腐処理または防蟻処理(木造)
・外壁軸組への防腐処理または防蟻処理(木造)
・床下の防湿性向上(木造・鉄骨)
・床下の点検口の取付(木造・鉄骨)
・雨どいの軒または外壁への取付(木造)
・地盤の防蟻処理(木造)
・給水管や給湯管、排水管の維持管理または更新の容易性(木造・鉄骨・RC)
減税を受けるための条件は以下のとおりです。
・耐久性向上リフォームを行う人が所有・居住している家である
・リフォーム後の床面積が50㎡以上
・床面積の2分の1以上が居住用
・長期優良住宅の認定を受けている
・一定の耐久性向上リフォームに加え、一定の耐震改修または一定の省エネ改修(もしくは両方)を行っている
・標準的な工事費用相当額から、補助金などを差し引いた金額がそれぞれ50万円を超えている
・2025年12月31日までに改修工事が完了し、居住している
・工事を行った年の合計所得金額が2,000万円以下
・その他減税を受けたい増改築工事がある場合、その工事は減税対象の工事になっている
・リフォームが完了してから6ヶ月以内に居住している
長期優良住宅化リフォームの最大控除額は、それぞれの工事によって異なります。
・耐震または省エネに加え、耐久性を向上させるための工事を行った場合:62.5万円
・上記の工事に加え、太陽光発電設備の設置工事を行った場合:67.5万円
・耐震+省エネ+耐久性の工事を行った場合:75万円
・上記の工事に加え、太陽光発電設備の設置工事を行った場合:80万円
・子育て対応リフォーム
子育てがしやすい家にリフォームした場合も控除が受けられます。
対象となる工事は以下のとおりです。
・家屋内に子どもの事故を防ぐための工事がなされている(クッションフロアへの交換やチャイルドフェンスの設置など)
・対面式キッチンへの交換工事
・開口部の防犯性を高める工事(防犯性の高い玄関ドアへの交換や割れにくい窓への交換など)
・収納設備を増設する工事
・防音性を高める工事(窓の防音性を高める工事、マンションは界壁・界床の防音性を高める工事)
・子ども部屋の増設や水回りの近接工事などの間取り変更工事
子育て対応リフォームで控除を受けるためには、さらに以下の条件を満たす必要があります。
・リフォームを行う人が以下のいずれかに該当している
①19歳未満の扶養親族を有している
②自分または配偶者が40歳未満
・子育て対応リフォームを行う人が所有・居住している家である
・リフォーム後の床面積が50㎡以上
・床面積の2分の1以上が居住用
・長期優良住宅の認定を受けている
・標準的な工事費用相当額から、補助金などを差し引いた金額がそれぞれ50万円を超えている
・2024年12月31日までに改修工事が完了し、居住している
・工事を行った年の合計所得金額が2,000万円以下
・その他減税を受けたい増改築工事がある場合、その工事は減税対象の工事になっている
・リフォームが完了してから6ヶ月以内に居住している
子育て対応リフォームの最大控除額は62.5万円です。
リフォームで活用できるその他の非課税措置

所得税以外の税金からも控除を受けられる制度があるので、確認していきましょう。
固定資産税の減税措置
1つ目が固定資産税の減税措置です。
耐震やバリアフリー、省エネ、長期優良住宅のいずれかでリフォームを実施すると、工事が完了した翌年以降の固定資産税が減額される仕組みです。
軽減額は、住宅の種類によって異なります。
各割合は以下の通りです。
・耐震:2分の1
・バリアフリー:3分の1
・省エネ:3分の1
・長期優良住宅:3分の2
申請する場合は、工事が完了してから3ヶ月以内に市町村に所定の書類を提出し、申告の手続きをします。
工事を確認できる書類の提出が必要になるため、あらかじめリフォーム会社に伝えて確実に用意してもらってください。
贈与税の非課税措置
年間110万円を超える贈与には贈与税が発生します。
しかし、リフォーム資金として祖父母や親から贈与を受けた場合は、最大1,000万円までの非課税措置をうけることが可能です。
ただし、以下の要件を満たしている必要があります。
・両親もしくは祖父母からの贈与である
・贈与を受けた年の合計所得額が2,000以下
・自己所有かつ居住している住宅に対する工事である
・リフォーム費用が100万円以上
リフォームローン控除の併用は可能?

リフォームローン控除の併用は種類によって可能なものもあれば、できないものもあります。
併用可能な控除は以下からチェックしてみてください。
・耐震リフォーム
併用可能:バリアフリー・省エネ・同居対応・住宅ローン控除
併用不可能:長期優良住宅化
・バリアフリーリフォーム
併用可能:耐震・省エネ・同居対応・長期優良住宅化
併用不可能:住宅ローン控除
・省エネリフォーム
併用可能:耐震・バリアフリー・同居対応
併用不可能:長期優良住宅化・住宅ローン控除
・同居対応リフォーム
併用可能:耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化
併用不可能:住宅ローン控除
・長期優良住宅化
併用可能:バリアフリー・同居対応
併用不可能:耐震・省エネ・住宅ローン控除
・住宅ローン控除
併用可能:耐震
併用不可能:バリアフリー・省エネ・同居対応・長期優良住宅化
リフォームローン控除を受けるための確定申告の流れ

リフォームローン控除を受けるためには、入居した翌年に確定申告をしなければいけません。
以下に確定申告の流れを解説していきましょう。
申告方法を決める
確定申告の方法として、青色申告と白色申告の2種類が用意されています。
申告する際には、どちらを選択するかあらかじめ決めておきましょう。
それぞれの内容を解説していきます。
青色申告について
定められた帳簿に記帳して記録に基づいて確定申告を行う制度が青色申告です。
複式簿記または簡易帳簿のいずれかで記載します。
簿記の形式によって控除額に違いがあり、最大65万の控除を受けることが可能です。
その他にも、55万・10万円の控除が受けられる方法があります。
それぞれの対象者は以下の通りです。
・最大65万の控除を受けられる対象者
複式簿記で記帳をして貸借対照表と損益計算書を添付している、かつe-Taxによる申告もしくは電子帳簿保存を実施している者
・最大55万の控除を受けられる対象者
複式簿記での記帳と貸借対照表と損益計算書の添付をしているものの、e-Taxによる申告もしくは電子帳簿保存をしていない者
・最大10万の控除を受けられる対象者
簡易簿記での記帳をしている者
また、青色申告の対象となる所得は限られています。
不動産所得、事業所得、山林所得の3種類のみが青色申告ができる所得となるため、それ以外の給与所得や譲渡所得、配当所得や退職所得では青色申告ができないので注意してください。
白色申告について
白色申告は、青色申告の承認を受けていない者が行う申告納税制度です。
青色申告のように複式簿記による記帳を行う必要がありません。
事前申請も必要ないため、書類作成の手間がかからない点がメリットです。
しかし、青色申告のような節税効果が望めない点がデメリットとなります。
事業を開始したばかりで事業収入が少ない場合は、控除の恩恵も少なくなるため手間のない白色申告の方が負担なく申告できるはずです。
作成方法を選択する
申告方法を決めたら、次に申告書の作成方法を選びましょう。
作成方法は4種類あります。
確定申告書作成コーナーでの作成
国税庁のWebサイトにある「確定申告書等作成コーナー」で作成する方法です。
必要事項を入力するだけで確定申告書を作成できます。
国が提供しているツールなので、安心して利用できる点がメリットです。
納税額も自動で計算されるので、自分で計算する必要がありません。
確定申告書作成コーナーで作った申告書は、印刷をして税務署に持参する他、インターネットを活用して税務署に送信することができます。
税務署への郵送も可能なので手間がかかりません。
ただし、ネット経由で税務署に送信する場合は、あらかじめe-Taxの事前準備が必要になるため注意してください。
確定申告ソフトを活用して作成
確定申告や申告に必要となる計算を行ってくれる確定申告ソフトを活用して申告書を作成することもできます。
必要な項目を入力するだけで作成できるため負担がない点がメリットです。
クレジットカードや銀行口座との連携も可能なので、仕分け作業もスムーズです。
スマホで使えるソフトもあるので、隙間時間での作成も可能です。
基本的には無料で利用できますが、中には一部機能のみ有料で提供しているソフトもあるため、前もって確認しておきましょう。
手書きで作成する
紙の確定申告書を用意して手書きで作成する方法です。
確定申告書は、税務署に取りに行く他、申告相談所や自宅やコンビニでプリントアウトして入手できます。
申告期間内であれば税務署に申告書を持ち込んで相談しながらの作成も可能です。
国税局電話相談センターに電話をして相談することもできますが、手書きなので時間がかかる点がデメリットです。
記入の仕方を理解していなければさらに時間がかかるため、事前に申告書の内容を理解しておく必要があります。
士業に依頼をする
税理士に確定申告の代行を依頼することも可能です。
税理士に対しての報酬が必要になりますが、正確な内容で申請ができる点がメリットです。
確定申告に対しての不安が大きい方や申告内容が複雑な場合は、税理士への依頼を検討してみてください。
申告書類の準備を行う
確定申告の内容に寄って用意する書類は異なりますが、基本的には以下の書類が必要です。
・確定申告で作成する書類
確定申告書
収支内訳書もしくは青色申告決算書
固定資産台帳
・確定申告で用意するもの
領収書やレシート、帳簿など
源泉徴収票
保険料控除明細書
医療費控除の明細書
寄付金の受領書
マイナンバーカード
金融機関の口座情報
固定資産がある場合は、帳簿類の他に固定資産台帳も必要です。
給与所得がある場合は、源泉徴収票も必要になるため忘れずに用意しましょう。
勤め先が2ヶ所あれば、それぞれの会社の源泉徴収票が必要です。
マイナンバーカードに関しては、個人番号が確認できるもので構いません。
扶養控除や配偶者控除を適用するためには、家族のマイナンバーを記載しなければいけないため、家族分のマイナンバーカードも用意しておきましょう。
申告書を提出する
申告書の提出方法は4種類あります。
・電子申告
・税務署へ持参
・郵送
・時間外収集箱への投函
電子申告は土日祝日を含む全日利用できるので便利です。
税務署に持参する場合は、納税地を管轄する税務署に提出してください。
税務署の営業時間外のみしか提出できない場合は、時間外収集箱への投函を検討しましょう。
また、郵送する場合は信書である必要があるため、書留や簡易書類で送る必要があります。
税金の納付もしくは還付
確定申告をすると納税額が決定します。
納税する場合は、納付書を使用して納めましょう。
納税期限は原則3月15日となりますが、猶予期間が欲しい場合や現金での納税が面倒であれば、振替納税の利用を検討してください。
事前に口座振替依頼書を提出することで、納付期限がくると自動的に所得税が引き落とされる仕組みです。
引き落とし日は4月下旬頃となるため、現金納付と比較すると1ヶ月程度の猶予があります。
還付となる場合は、1~2ヶ月程度で国税還付金として指定した口座に入金されます。
電子申告をすると2~3週間程度で還付金が入金されるので、早く受け取りたい場合は電子申請を選択しましょう。
リフォームローン控除を受けるために必要な確定申告の書類
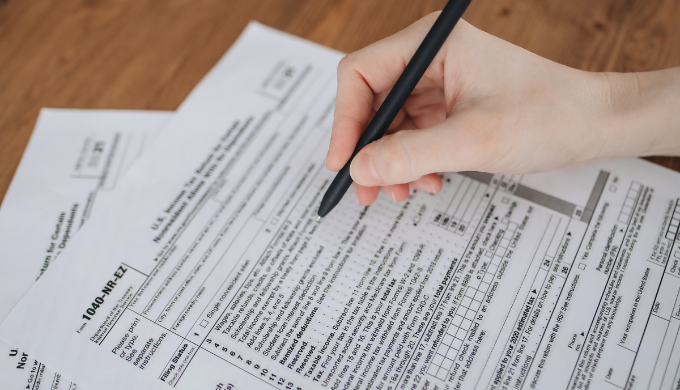
リフォームローンの控除を受けるためには書類を用意する必要があります。
用意すべき書類はリフォームの種類によって異なるので、事前に把握しておくとスムーズな申請が可能です。
必要な書類
まずは、基本的に必要となる書類について解説していきます。
事前に用意をして確定申告書と一緒に提出しましょう。
・確定申告書
1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとにして税額を計算、申告、納税するための書類を確定申告書と言います。
国税庁のホームページからダウンロードできるだけではなく、税務署でも受け取ることが可能です。
確定申告書には、第一表から第四表まであり、リフォームで住宅ローン控除を受けるためには第一表と第二表が必要です。
・住宅借入金特別控除額の計算明細書
リフォームによって住宅ローンをいくら受けられるか計算するための書類です。
リフォームをする際に必要となった費用や補助金額、年度末時点でのリフォームローンの残高などを記入する必要があります。
・登記事項証明書
リフォームをして増築や減築によって住宅の面積が変わった場合には、登記事項に変更があるので登記変更手続きをしなければいけません。
また、住宅ローン控除を受けるためには床面積が50㎡以上である必要があるため、それを証明するためにも必要な書類となります。
・補助金額がわかる書類
国や自治体の補助金を受けた場合は、リフォーム費用から差し引いて控除額を計算しなければいけません。
もし、補助金を受けたのであれば、「補助金決定通知書」といった書類を無くさないように保管しておいてください。
・リフォームローンの年末残高証明書
年度末時点でのリフォーム残高に0.7%をかけたものが控除額です。
そのため、控除額を計算する際には欠かせない書類です。
リフォームローンを借りている金融機関から送られてくるので、紛失しないように保管しておきましょう。
・源泉徴収票
確定申告の際に添付する必要はなくなりましたが、所得や生命保険料控除を記入する際に必要となります。
税務署で申告書を作成する時にも必要になるため、忘れずに持参しましょう。
・増改築等工事証明書
工事内容を証明する際に必要となる書類です。
一級建築士や二級建築士、指定確認検査機関や登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した書類である必要があります。
第1号工事のみ、建築確認を伴うリフォームであれば確認済証の写しや検査済証の写しを提出するだけで良いため、増改築等工事証明書は必要ありません。
・工事請負契約書の写し
リフォーム工事での費用や補助金を差し引いた額が100万円を超えているか証明するために必要な書類です。
リフォーム工事を契約する際にリフォーム会社から発行されます。
工事請負契約書がない場合は、領収書や工事費用内訳書でも構いません。
リフォーム別必要書類
リフォームの種類によって必要な書類は異なります。
ここでは、リフォームごとに用意すべき書類をご紹介していきましょう。
・耐震リフォーム
控除額計算明細書
補助金額がわかる書類
登記事項証明書
源泉徴収票
工事請負契約書の写し
増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
・長期優良住宅化リフォーム
住宅特定改修特別税額控除額計算証明書
登記事項証明書
長期優良住宅の認定通知書の写し
補助金額がわかる書類
源泉徴収票
工事請負契約書の写し
増改築等工事証明書
・省エネリフォーム
住宅特定改修特別税額控除額計算証明書
登記事項証明書
補助金額がわかる書類
源泉徴収票
工事請負契約書の写し
増改築等工事証明書
・バリアフリーリフォーム
住宅特定改修特別税額控除額計算証明書
リフォームローンの年末残高証明書
登記事項証明書
補助金額や居宅介護住宅改修費額がわかる書類
源泉徴収票
工事請負契約書の写し
増改築等工事証明書
今回は、リフォームローン控除について解説してきました。
住宅が古くなればリフォームが必要です。
しかし、費用がかかるため、減税や優遇制度、補助金などを活用して余裕のあるリフォームを計画する必要があります。
住宅ローン控除やリフォーム減税、固定資産税の減税といった制度について、あらかじめ仕組みを理解しておきましょう。
また、リフォーム控除を受けるためには確定申告が必要です。
必要な書類や流れに関しては、今回ご紹介した情報を参考にして手続きを行ってみてください。




